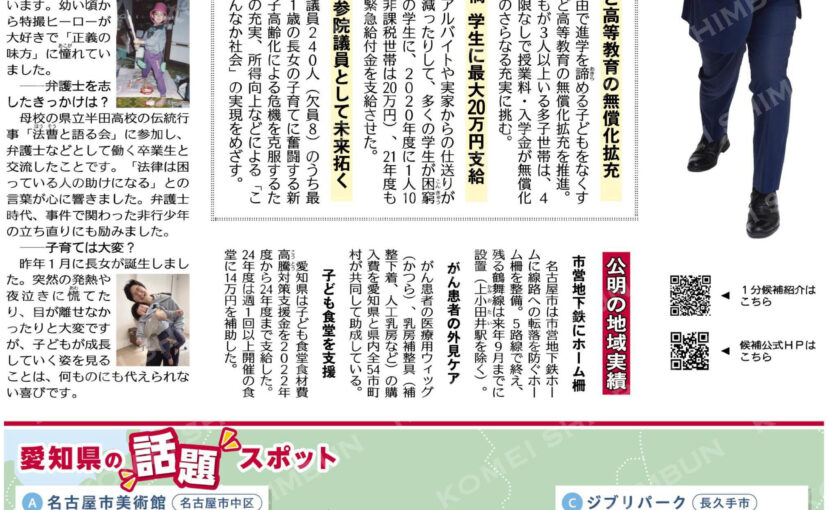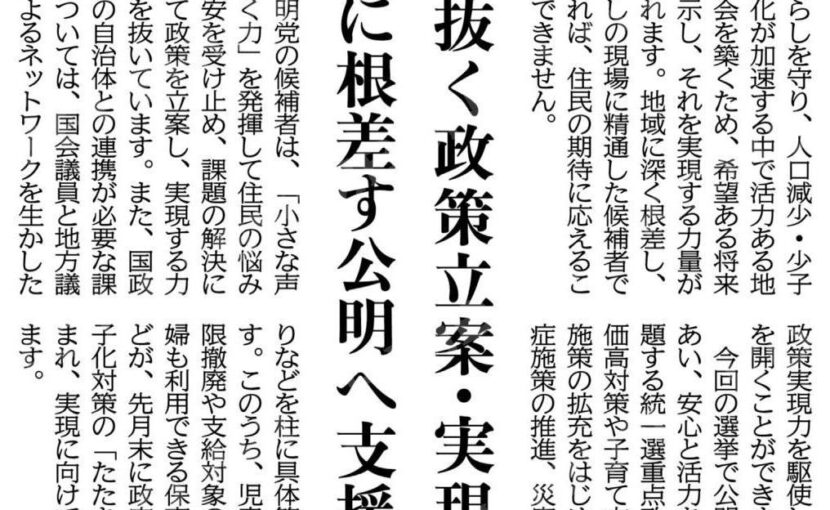議事録
第211回国会 参議院 農林水産委員会 第3号 令和5年3月17日
安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。質問の機会をいただき、ありがとうございます。
初めに、輸出小麦の政府売渡価格のことに関連してお伺いをしたいと思います。
三月の十四日、令和五年四月期の小麦の政府売渡価格について、上昇幅を一部抑制する激変緩和措置講じられることが発表されております。
我が党といたしましても、予算委員会の質疑あるいは農水部会等を通じ、政府に対して消費者等の皆様の負担が上昇しないよう配慮した対応を求めてきたところであります。この度の対応については、まずは感謝を申し上げたいと思っております。ただ、その上で、実際には価格は上がる、消費者の皆様の負担感は増し、また将来に対する不安も増大をするところかと思います。
そうしたところから、政府のこのような取組については、まずはしっかりと情報の発信に努めていただきたいということと、また引き続き今後の価格動向を注視していただきまして、関係者、とりわけ消費者の負担が急増しないような配慮を継続的にお願いをしたいと思います。野村大臣の御所見をお伺いします。
国務大臣(野村哲郎君) この問題につきましては、委員会、あるいは決算委員会、農林水産委員会や衆参でもいろいろ御要望なり御検討がいただいておるところでありますが、そのときにも御答弁申し上げておりましたとおり、総理からの指示によりまして激変緩和措置をとらせていただいたところでございます。
ただ、ウクライナ侵略後の急騰の影響を受けた期間を除いて、そして直近六か月間の買い付け価格を反映して、そして五・八%という数字が出てきたわけでありますが、上昇幅を抑制することとし、十四日に私の方から発表をさせていただきました。
これらにつきましても、各種の説明会を開催しながら丁寧な説明をしていきたいと、そして情報発信をしていきたいというふうに思っておりまして、総理からもう一つ宿題をいただきました。宿題というよりも指示をいただきましたのは、翌期以降についても、今後の小麦の買い付け価格に基づいて決まるものでありますが、その動向を注意深く注視しておいてくれと、こういう指示もございましたので、十分その辺を踏まえながら検討してまいりたいと思います。
安江伸夫君 引き続き、よろしくお願いをいたします。
続きまして、酪農を始めとした畜産の支援に関連してお伺いをしたいと思います。
これまでも国会におきまして繰り返し議論されてきているテーマでございますけれども、私も地元愛知県の声を伺ってまいりましたので、御質問させていただきたいと思います。
飼料等の価格高騰を受けまして、とりわけ酪農家の営農の危機が叫ばれ続けております。地元の愛知県豊橋市の畜産・酪農農家の皆様からも非常に厳しいお声を私自身たくさんいただいているところでございます。
公明党といたしましても、先般、三月の十五日、飼料等の価格高騰対策など、引き続きの支援をお訴えさせていただいたところでございますが、改めて、酪農家を守り、酪農産業を維持していくためにも、営農継続に向けた支援をお願いしたいというふうに思います。
また、実際、私も現場には、県政やまた地元の市議との連携、こうしたことをやっていくことが重要だというふうに考えておりまして、各自治体での取組も様々、地方創生臨時交付金等を活用して行われているところでもございますので、農水省としてもこうした地方独自の取組も後方支援をしていただきたいというふうに思います。足下での酪農家の窮状に関する野村大臣の御所見をお伺いします。
国務大臣(野村哲郎君) 大変、これはこの委員会でも質問なりあるいは御意見をいただきまして、酪農経営の危機が叫ばれておるわけでありますが、そのときにも申し上げてきたところでありますけれども、総理の指示によりまして、まずは四年度の四半期、今年の一月から三月までの価格をどうするかというのが一つありました。それから、御要望の多かった粗飼料の高騰に対する対策をどうするかというのが二つ目。それから三つ目は、言わば高止まりしているときの補填というのは制度に合わないんじゃないかと、こういうような御質問なり御要望もいただいておりましたので、それらを検討をずっとしてきております。
まだ四半期の、四・四半期の価格をどうするかというのは、まあ前提は昨年の三・四半期並みのという、激変緩和措置を講ずることということが総理の指示でありますから、それを基本にしながら今検討を進めておって、まだ幾らですということは申し上げられる時期ではありませんけれども、大体昨年の三・四半期並みの価格、こういうところをベースにしながら検討させていただいております。
それから、購入粗飼料の高騰対策についても、これも一回対策を打ったことがありますから、それをベースにしながら検討を進めておるというのが二つ目です。
それから三つ目は、四・四半期以降の、四月から以降どうするかというのは、これは今の制度の中でやるのか、あるいは別な制度をつくっていくのか、まあいろんな考え方もあろうと思うんですが、これらについては十分ないろんな状況を見据えながら検討を進めていかなきゃならないということでありますけれども、これについても激変緩和対策をやっぱりやっていかなきゃいけないだろうと、こういうことは内部では検討しているところでございます。
安江伸夫君 是非ともよろしくお願いしたいと思います。
残念ながら、既に愛知でも離農された方もいらっしゃるということも伺っております。こうした人がもう一人でも出ないような、そういう決意で臨んでいただきたいことをお願いしたいと思います。
続きまして、国は酪農経営の支援に関して、需要の底上げを図るとともに、抑制的な生産の取組に対する支援などを通じた需給ギャップの解消、この解消を掲げていると承知をしております。もっとも、生乳の生産能力を減らし過ぎてしまうことは将来の需給回復を見据えたときにリスクが大きいという声もございます。需要と供給のバランスを考えた中長期的な視野に立った戦略が必要と考えます。目の前の危機に対して需給ギャップ解消の必要性を否定するものではございませんけれども、酪農というインフラというべき産業を維持していくために、中長期的な営農支援の視点も重要と考えます。野村大臣の御答弁を求めます。
政府参考人(渡邉洋一君) お答えをいたします。
当面の最大の課題でございますが、生乳の需給ギャップの解消と生産コスト上昇の乳価への適切な反映であります。牛乳・乳製品の消費拡大のほか、生乳の生産抑制についても自主的な取組を支援することとしてございますけれども、生産抑制については、将来生乳が不足することがないように、生乳生産量ですとか乳製品の在庫量などの動向を注視しながら的確に実施したいと考えてございます。
また、中長期的には、輸入飼料への過度の依存から脱却をいたしまして、国内の飼料生産基盤に立脚した酪農経営への転換を図っていくことが重要でありまして、耕種農家が生産した飼料を畜産農家が利用する耕畜連携の推進、地域の飼料生産を担うコントラクターなどの飼料生産組織の運営強化、国産粗飼料の広域流通への支援など、国産飼料の生産、利用拡大などの各種対策を講じていきたいと考えてございます。
安江伸夫君 じゃ、この点、大臣にも御答弁をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
国務大臣(野村哲郎君) 先ほどちょっと申し上げましたけれども、いろんな対策はあると思うんですが、どういうところからやった方が農家の方々が今後安定した経営ができるのかというのが我々一番悩むところであります。
したがいまして、畜産経営の安定というのは、価格のこの補填というのも一ついろいろ御意見があるようなこともあるんですけれども、一つは、やっぱり飼料代が高くなっていると。その中でも、規模拡大をやった、そして粗飼料は外国から輸入する。この粗飼料代というのが、それまでは非常に安かったわけですが、ここに来まして相当値上がりをいたしました、三倍ぐらいになっていると思いますが。こういう粗飼料への過度の、まあ輸入粗飼料に対する過度な依存というのがあるのではないかということで、国内の粗飼料生産基盤に立脚した足腰の強い酪農への転換を図ることが必要だと。
私は、もう口癖のように地元の酪農家の皆さん方にはそのことを申し上げて、まずは草作りからですよということを申し上げておるところでありまして、やはりそこのところは私はキーになってくると。粗飼料代で、もう非常に、どうにもやれなくなったと、決済ができなくなったというような話も聞いておりますので、やはり、粗飼料というのはやっぱり自分のところで作るべきだろうと、まあこんなふうに思っているところでございます。
そういう意味でも、酪農家の皆さんが将来展望を持って経営ができるように、そうした国産飼料の生産あるいは利用の拡大等の各種の対策を講じてまいりたいと思っております。
安江伸夫君 大臣、ありがとうございました。
今の飼料にも関連してもう一問お伺いをさせていただきますが、国は令和十二年度までに、今もありましたけれども、粗飼料、これを一〇〇%、目標に掲げております。また、飼料自給率につきましても三四%という数値を掲げているものと承知をしております。食料安全保障の観点からも飼料の自給率を着実に上げていくことは大変に重要であり、強力な支援を今の大臣の御答弁にもあったとおり、お願いをしたいと思います。
ただ他方で、その上で、畜産クラスターの取組なども通じて飼料自給率向上に向けた施策を推進していただいておりますところ、例えば私の地元愛知県の酪農家の皆様等からは、比較的都市部に近いところで酪農を行っている皆さんの声になりますけれども、担い手が不足している、地域的にまとまった土地がなく効率化をしにくい、新規の設備投資には補助があってもランニングコストの不安から利用しにくいといった厳しい声も寄せられているところでございます。
飼料自給率の向上を目指すとしても、例えば愛知県のような都市部に近いところで酪農を経営している方の声にも寄り添った政策を推進をしていただきたいと思います。農水省の御所見をお伺いします。
政府参考人(渡邉洋一君) お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、我が省といたしましては、飼料自給率を二五%から令和十二年度に三四%に引き上げる目標ということを目指しまして対策をしてございます。
土地がなかなかないとか労働時間が取れず餌が作りづらいとかという酪農家さんの現実も踏まえまして、耕種農家さんが生産した飼料を畜産農家に利用していただくような耕畜連携の推進ですとか、コントラクターのような飼料生産組織の運営強化などを行ってございます。
また、都市部を含む各地域の現場の声も聞きながら丁寧に対応している中で、先ほど大臣からもございましたけれども、物価本部での総理からの御指示も踏まえまして、今、飼料のコストの抑制をするというようなことで具体的な対応を検討しているところでございます。
安江伸夫君 ありがとうございました。是非、引き続き現場の声を聞いていただき、私自身も現場の声をしっかりと届けてまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、農林水産物等の輸出に関連をしてお伺いをしたいと思います。
国内の農林漁業、食品産業の発展を目指して輸出拡大を進めることは重要と考えます。もっとも、輸出力の強化を推進したことによって我が国の食料自給率が低下するようなことは決してあってはなりません。
そこで、輸出力強化に関しては、単に稼ぐという観点のみならずして、それを通じて我が国の農業、漁業等の産業を守り、農地を守り、発展させ、ひいては食料安全保障を強化するという視点と、また戦略性を持って取り組んでいただきたいと思います。野村大臣の御答弁を求めます。
国務大臣(野村哲郎君) お答え申し上げます。
輸出の拡大は、海外の新たな需要を取り込む形で生産を拡大することによりまして、一般的に、食料自給率を向上させ、食料安全保障を強化する効果を持つというふうに考えております。
委員御指摘のとおり、輸出拡大に当たっては、我が国の農林水産業を守り発展させていくという視点が必要でございまして、国内生産向けに、国内向けに生産されたものを単に高く販売できるというだけの事情で海外に持ち出すというよりも、マーケットインの発想で、海外の需要に応じて国内の生産を拡大する取組を促していくべきだと考えているところでございます。
このため、農水省におきましては、十二月に改訂されました輸出拡大実行戦略に基づきまして、大ロット輸出産地のモデル形成を支援していく、あるいはまた、輸出支援プラットフォームが連携したリレー出荷を可能にする、こういったような取組をしているところでございます。
今後とも、輸出の拡大が、農林水産業の所得向上に向けて、農林水産業の維持拡大や食料安全保障の強化に資するように戦略的に対策を進めてまいりたいと思っております。
安江伸夫君 大臣、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
また、輸出の拡大に際しましては、効率的な物流を実現するために地域の空港や港湾を利用することが重要かと考えます。昨年審議されました輸出促進法等の改正案に対する本院の附帯決議におきましても、高鮮度で付加価値の高い輸出物流の構築や輸出に係るコストの低減のために、輸出産地との密接な連携が必要となる地域の空港や港湾の活用を推進することと求めているところでございます。
また、今後、輸出量が増大していくことが予想される中で、トラックドライバーの時間外労働の規制が強化される物流の二〇二四年問題への対応も含めて、輸出産地への近くに立地する空港や港湾を利用していくことが重要と考えます。
地域の空港や港湾の活用状況と今後の取組方針につきまして、藤木農林水産大臣政務官にお伺いします。
大臣政務官(藤木眞也君) お答えをいたします。
農林水産省では、効率的な輸出物流の構築に向けて、物流の二〇二四問題も踏まえて、国内の長距離輸送を避け、輸出産地の近隣に立地する地方の空港や港湾を活用した輸出の促進に取り組んでいます。
具体的に言えば、例えば北海道においては、新千歳空港、また苫小牧港などの物流拠点に接する産地、物流事業者、行政などの関係者によるネットワークを形成し、混載などの実証を支援するほか、生鮮品の通関先を主要空港から例えば青森空港や小松空港など産地に近い地方の空港での通関に変更することで輸送コストの削減や輸送時間の短縮を図る実証を支援しております。
引き続き、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。
安江伸夫君 ありがとうございました。
済みません、ちょっと時間の都合上少し質問の順番を変えさせていただきまして、最後のテーマである食品アクセスの問題に関連してお伺いをさせていただきたいと思います。通告の十一番の質問になります。
高齢化や単身世帯の増加、地元小売業の廃業等によりまして高齢者を中心に食料品の購入や飲食に不便を感じる方、いわゆる食品アクセスの問題として社会的な課題となっております。これにつきましては、農林水産政策研究所の調査、食料品アクセス困難人口として調査をされているところでございますが、引き続き各自治体において効果的な対策を講じていくためにも、この食料品アクセス困難人口の最新状況を把握すべきものと考えます。藤木政務官にお伺いします。
大臣政務官(藤木眞也君) お答えをいたします。
食料品アクセス困難人口について、二〇一五年時点の推計値を二〇一八年に公表したところです。この推計は国勢調査などを基におよそ五年に一度公表しているところであり、現在、新しい推計の作業を進めているところでございます。遅くとも本年中を目途に結果を公表してまいりたいと考えております。
安江伸夫君 大変、自治体が政策を打つに当たって重要なデータになるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
最後の質問とさせていただきます。
引き続き食品アクセスの問題に関連してでございますが、農水省は毎年、全国の市町村を対象にアンケート調査を食品アクセスの問題に関連して行っていただいているものと承知をしております。こうしたアンケートの結果をしっかりと踏まえていただきまして、各種課題等もたくさん上がっているところでございます。引き続き、この食品アクセスの問題、農水省としても積極的に取り組んでいただきたいというふうに考えております。
食品アクセス問題についての農水省が果たすべき役割について、こちらは勝俣副大臣にお伺いをいたします。
副大臣(勝俣孝明君) ありがとうございます。
委員御指摘のとおり、アンケート調査を実施しておりまして、そもそも対策を実施する事業者がいない、地域の現状や課題の分析が不足している等の課題について回答を得ております。
このような状況を踏まえ、農林水産省としましては、移動販売車や無人型店舗の実証試験の支援を行うほか、農林水産省のホームページに食品アクセス問題ポータルサイトを設けて、農林水産省を始めとした各府省の支援策や地方公共団体での取組事例の紹介等を行っているところであります。
引き続き、関係省庁と連携しながら、食品アクセスの確保に努めてまいりたいと考えております。
安江伸夫君 ありがとうございました。
この食品アクセスの問題、ますます深刻化、都市部、また地方も、両方の地域において問題深刻化していくと思いますので、引き続きの対応をお願いしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。